日常。
仕事(ケーキ)とテニプリのことばかり。
小話第二段。
めいんの方に置いてある『色仕掛け~』の続編を書こうとしていたら思いついた副産物です。
『色仕掛け~』の冒頭とこの話の出だしはほとんど同じです。
あっちは割りとおちゃらけていたので、こちらは割と真面目に。
書いていて、この仁王やたら奥手だなぁ…仁王のくせに
と思っていました(笑)
興味のある方は続きからどうぞ
めいんの方に置いてある『色仕掛け~』の続編を書こうとしていたら思いついた副産物です。
『色仕掛け~』の冒頭とこの話の出だしはほとんど同じです。
あっちは割りとおちゃらけていたので、こちらは割と真面目に。
書いていて、この仁王やたら奥手だなぁ…仁王のくせに
と思っていました(笑)
興味のある方は続きからどうぞ
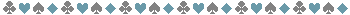
どうにか堪えるが、気管に入ってしまい咽せる。
…前にも同じ様な事があったような気がする。仁王はかすかな記憶を探ったが、面倒になったのですぐに止めた。
昼休みの喧騒が遠くで微かに響いているが、屋上庭園はこの上なく静かだ。
幸村と仁王以外に人はおらず、秋の高い青空と冷たくなりつつある風を感じながら幸村は花壇をいじる事に、
仁王はぼうっとシャボン玉を吹く事に専念していた…はずである。
何故その心地良い沈黙を破る一言が、そんな突拍子もない物なのだろう。
「何じゃ、また唐突に」
「別に~?それより答えは?俺達ももう部活は引退したんだし、お互いに幸せな相手がいるんだからもう時効って事で。白状しちまえよ」
花壇の手入れが終わったのか、幸村が立ち上がり仁王の隣へやって来る。
どうやら、拒否権は存在しないようであった。
そのあたりの傲慢さが、実に幸村らしいと思う。
だがこうして皆何やかんや言いつつも、その我が儘を聞いてやってしまうという事がさらに幸村の傲慢加減を悪化させているのだ。
自分だけは違うと思っているのは本人だけである。
「だったら何だっちゅーんじゃ?」
「別にどうもしないよ。俺の知的好奇心が満たされるだけ」
「どーしよーもない知的好奇心じゃな」
うっかり本音を漏らすと、幸村から拳骨が飛んできた。
思い切り食らってしまい、頭を抱えてしばし悶絶する。
幸村は華奢なくせに意外に力が強い。
一体どこにそんな腕力があるのだと突っ込みたくなるくらいに。
「暴力反対じゃ」
「俺が聞いてるのに答えない仁王が悪い」
何だその俺様的思考回路、と仁王は思ったが、それをくちにするとまた拳が飛んでくるだろう事は予想できたので、大人しく口をつぐんでおく。
かわりに、一つため息をついた。
「仕方ないのぅ。内緒ぜよ?」
周囲を確認して人気がないことを確かめる。
万が一柳などが聞き耳を立てていると厄介だ。あの参謀に弱みを握らせると何を迫られるかわからない。
…もっとも、柳のほうも仁王をそのように認識しているのだろうけれど。
「…好きだったぜよ。ずっと気になっとった。けどお前さんの側には常に真田か参謀がおったからのぅ」
「ふーん」
「しっかし…気づかれとるとは思わなかったぜよ」
「気づくよ。…俺も仁王の事すきだったからさ」
「ほーう。………なに?」
ぽつりと呟かれた幸村の言葉。
何の気無しに聞き流した仁王であったが、しばらくたってからその言葉の意味を理解する。
ガバっと勢いよく幸村の方を見れば、自嘲気味な笑いを浮かべた姿がそこにはあった。
幸村がぽつぽつと語る。
「俺もそのころ仁王のことが好きだった。でも俺と仁王は似てるから、一緒にいたらダメになると思った」
「似とる、か。…確かにダメになっとったかもしれんのぅ」
真田と幸村がコインの表裏のような関係であると評するならば、仁王と柳生もまた然り。
幸村と仁王はよく似ている。
本心を隠し通すところも、悩んでも一人で抱え込むところも。
そうであるが故に、相手のことがわかる。わからなくてよい部分までわかってしまう。
距離が縮まれば、なおの事。
「さーて、そろそろ教室帰ろうかな」
しばらく幸村は黙って空を見上げていたが、突然そんなことを言って勢いよく立ち上がった。
それまでの雰囲気がうそであったかのように、普段の明るくて傍若無人な幸村精市がそこにいた。
見計らったかのようなタイミングで、四例のチャイムが校内に鳴り響く。
「そうじゃな。そろそろ帰らんと」
「あ、仁王。待って、その前に」
同じく立ち上がろうとした仁王をベンチに押さえつけて、幸村がニンマリ笑った。
何かをたくらんでいる笑い。
いったい何だと仁王が身構えた瞬間。
勢いよく幸村に口付けられて思考回路が真っ白になった。
そしてしばしの間。
「…ゆき…っ」
「じゃぁね、仁王!」
仁王の唇から己のそれを離した幸村が、笑顔で走り去る。
仁王の呼びかけは見事に無視された。
一人屋上庭園に取り残された仁王は思う。
あぁ、これが最初で最後のキスか、と。
PR
この記事にコメントする
