思わず昼休みの間にちまちまとケータイで書いて、家に帰ってからお風呂で書いて。
思いついたのは昨日だったのですが、何やら完成したのでコチラにアップする事にします。
ケータイでちまちま書くと普通のSSとしてアップするにはちょっと短いので。
職場の人間関係がゴタゴタしていてウンザリしているのでこんなダークなものを思いついたのかもしれません。
まず冒頭の『目の前に幸村精市だったものの残骸が転がっている』というフレーズを思いついて、「あ、仁幸だ」となんとなく直感したのでそのまま妄想してました。(真面目に仕事しろよという感じです)
それだけでもわかる通り暗くてダークで救いようの無い、真幸前提・仁王視点の仁幸です。
私はこの手の話を書くのは大好きなのですが、書くたびに自分の文章力と語学力の無さにウンザリします。
読んでくださるお心の広い方は続きからドウゾ。
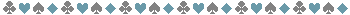
硝子の欠片(真幸←仁)
目の前に『幸村精市』だったものの残骸が転がっている。その瞳はもう睨む事は無いし、口から拒絶の言葉が出ることも無い。
殺した訳では無い。壊しただけだ。
粉々に、完膚無きまでに叩き割った。
それを、望んでいた筈だった。
だが壊れた『幸村精市』を見た瞬間、『それ』に対する執着が急速に衰えて行くのを感じた。
何故だろう。
彼は考える。
ずっと彼は『幸村精市』を愛していた。
しかし『幸村精市』には別の思い人が居り、彼らは相思相愛であった。
思い人の名を、真田と言う。
真田と共に居る『幸村精市』は幸せそうであった。
それを見て彼は『幸村精市』を手に入れるのは、どうやっても不可能なのだと言う事に気づいてしまった。
しかし、手に入らないと自覚すればする程『幸村精市』を己の物にしたいという欲求は強くなる。
そうしてある時ふと彼は思った。
手に入らないならばいっそ、壊してしまえ。
『幸村精市』は強かった。しかし、あまりに強いが故の弱さを内包している。
ピンと張り詰めた一本の糸を切ってしまえば、『幸村精市』を壊すことは容易い事を彼は長年の付き合いから見抜いていた。
『幸村精市』は、研ぎ澄まされた薄い硝子の様であった。
薄く美しいそれの端に不用意に触れれば、鮮やかなまでに切り裂かれる。
しかし、硝子というのは一度罅か入ってしまうと一切の強度が失われるのだ。
だが肝心なのは、どの点を突けば『幸村精市』が壊れるのか…である。その見極めが彼の観察眼を持ってしても、曖昧であった。
しかし、それは意外な第三者からの情報によって解決した。
第三者である彼の人物は、『幸村精市』と大層仲の良い人物であった。恋人でこそ無かったものの『幸村精市』を溺愛していると言っても過言ではなかった彼の人物が何故己に『幸村精市』の弱点を教えたのかは甚だ疑問ではある。
しかし彼にとって重要なのは、『幸村精市』を壊すことができる。この一点のみであった。
『幸村精市』に罅を入れるのは容易なことでは無かったが、一度罅が入ってしまえば後は呆気なかった。
しかしいくら眺めてみても、彼の目の前に転がる『それ』にかつてのような執着心を持つ事は不可能であった。
興醒めして、溜め息をつく。
最早『それ』に何の未練も無かったので、さっさと立ち去る事にする。
『それ』をそのまま放置し、踵を返して玄関へ向かう。
放っておけばさほどの時を置かずに帰ってきた真田が『幸村精市』の残骸を発見する筈だ。
その残骸を、粉々になった欠片を丹念に一つ一つ拾い上げて修復しようが深い嘆きの果てに絶望の淵へと転がり落ちようが知った事では無い。
玄関の扉を開き、外にでる前に『それ』をもう一度振り返る。
矢張り、何の感慨も浮かばなかった。
すぐに興味を失い、外に出る。
背後でバタンと音を立て扉が『幸村精市』と彼を隔絶した。
外は鉛色の冬空が広がり、風は身を切るかの如き冷たさであった。
その風に吹かれながら、改めて考える。
何故あれ程までに『幸村精市』を壊す事に執着していたのに、いざ壊してみれば途端に『それ』に対する感情が消え去ったのか、と。
行き先を決めぬまま冬の街を行く。
決して手に入らないからこそ、『幸村精市』を壊したいと言う欲求が大きくなって行ったのだろうか?
手に入らないからこその思いは、手には入った瞬間に色褪せて消えたのだろうか。
『ねぇ仁王。俺は今すごく幸せなんだ』
かつて『幸村精市』は彼にその様に告げた事があった。
あぁそうか。
仁王は思う。
俺は、あの硝子細工の様な強さを持った、生き生きと輝く『幸村精市』が好きだったんだ。
彼は一人、寒空の下冷たい雑踏を歩く。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
兎に角救いようの無いダークな話を目指してみました。
私にしては珍しく堅苦しい感じで書こうとして…撃沈。難しい。
というか、こんな事を考えながらケーキを作っている自分が一番救いようが無い気がします(苦笑)
